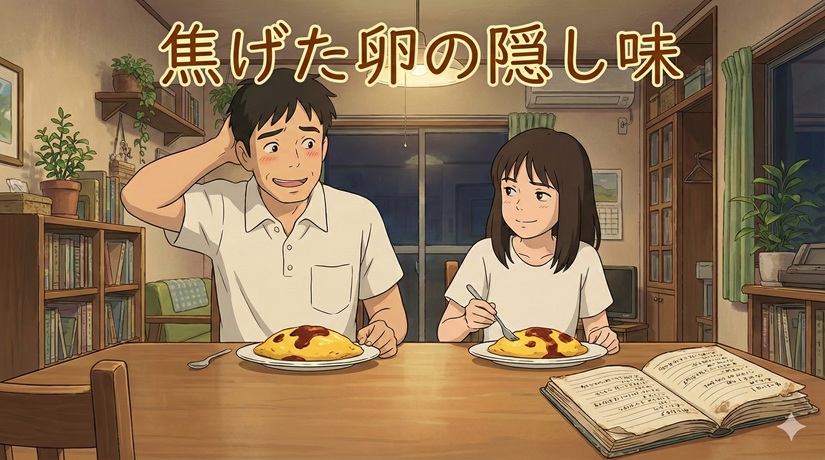「ねえお父さん、またこれ?」
高校二年生の美咲(みさき)は、ダイニングテーブルに置かれた弁当箱を覗き込み、呆れたように声を上げた。
黄色い鮮やかなキャンバスであるはずのオムライスの上に、点々と、いや、堂々と茶色い「焦げ」の斑点がついている。まるで、黄色いヒョウ柄だ。
「あー、ごめんごめん。火加減がどうも難しくてな」
父はトーストをかじりながら、頭をポリポリとかいた。母が亡くなって三年。父は毎朝、美咲のために弁当を作ってくれるのだが、どういうわけかオムライスを作る時だけは、決まって卵を焦がすのだ。
「味は悪くないんだから、文句言うなよ」
「文句じゃないよ。ただ、卵は『ふわとろ』が正義でしょ? クックパッド見れば誰でもできる時代に、なんで毎回『ガリガリ』なのよ」
美咲はため息交じりに弁当箱の蓋を閉じた。
父は仕事は丁寧だし、他の料理はそれなりに上手だ。なのに、オムライスだけは、まるで何かの呪いにかかったように失敗し続けている。
(不器用なのかな……)
美咲は、少しの罪悪感と、それ以上の諦めを抱えて学校へと向かった。
その週末、父が急な休日出勤で出かけていった。
昼食は自分で作らなければならない。美咲はキッチンに立ち、ふと「今日こそ私が、正真正銘の『ふわとろオムライス』を作って、父の舌を教育してやろう」と思い立った。
冷蔵庫から卵を取り出し、レシピを確認しようとして、美咲は食器棚の奥にある古びたノートのことを思い出した。
それは、生前の母が書き残していたレシピノートだ。父も時々これを広げては、ぶつぶつと独り言を言いながら料理をしている。
「えーっと、オムライス、オムライス……」
油や醤油のシミがついたページをめくる。懐かしい母の丸文字が現れた。
『我が家のオムライス』というタイトルの下には、ケチャップライスの具材や、隠し味に入れるウスターソースの分量が丁寧に書かれている。
そして、最後の手順のところに、赤ペンで追記がしてあった。
『※重要ポイント』
美咲は目を凝らした。そこに書かれていたのは、予想外の指示だった。
『卵を流し入れたら、あえて強火にすること。バターが少し焦げる香ばしい匂いがするまで待つ。パパは、半熟よりも、ちょっと焦げてカリッとした香ばしい卵が好きな変人だから、失敗したかな? くらいでちょうどいい』
「……は?」
美咲の声が、誰もいないキッチンに響いた。
失敗じゃなかった。
父は、不器用で焦がしていたわけではなかったのだ。
ただひたすらに、忠実に、「母さんが作ってくれていた味」を再現しようとしていただけだったのだ。
「なんだ、それ……」
美咲は、ノートの端をつまんだまま、キッチンカウンターに寄りかかった。
父の「火加減が難しくてな」という言葉が蘇る。あれは、下手くそな言い訳ではなく、照れ隠しだったのか。それとも、「母さんの味」を娘に押し付けていると思われたくなかったのか。
「変人は、お父さんだけじゃないじゃん」
美咲は苦笑いをした。あの焦げた卵を「我が家の味」として書き残した母も、それを律儀に三年も守り続けている父も、どっちもどっちだ。
泣きそうになるのをぐっと堪えた。ここで泣いたら、湿っぽいドラマになってしまう。それは我が家のキャラじゃない。
美咲はフライパンを火にかけた。
バターを落とす。ジュワッという音と共に、芳醇な香りが立つ。
溶いた卵を一気に流し込む。
いつもならここで火を弱めて、箸で手早くかき混ぜて「ふわとろ」にするところだ。
美咲は、コンロのつまみをひねった。
火力を、強める。
チリチリチリ……と、卵の縁が焼ける音が鋭くなる。バターの焼ける匂いが、少しだけ香ばしい焦げ臭さへと変わっていく。
いつも弁当箱を開けた時に香る、あの匂いだ。
「……これくらいかな」
美咲は、ほんのり茶色い焼き目がついた卵を、ケチャップライスの上に滑らせた。
見た目は、父が作るものよりはマシだが、世間の「映えるオムライス」からは程遠い、茶色い水玉模様のオムライスが完成した。
夜、父が帰宅した。
「おう、疲れたー。腹減ったなあ」
「お帰り。ご飯、できてるよ」
美咲がテーブルに出したのは、昼に練習して、夜用にまた作った「特製オムライス」だ。
父はそれを見て、目を丸くした。
「おっ、美咲が作ったのか? ……ん? なんか、卵の様子が……」
「いいから食べてみてよ」
父はスプーンを入れ、一口運んだ。
咀嚼する父の動きが、一瞬止まる。
口の中に広がるのは、バターのコクと、卵の甘み。そして、鼻に抜ける少しビターな焦げの風味。
「……どう?」
美咲が意地悪く聞くと、父は少しだけ目元を緩めて、ニカッと笑った。
「うん。……ちょっと火が強かったな。焦げてるぞ」
「うるさいな。それがレシピ通りなの」
「レシピ?」
「お母さんのノート、見たから」
父は「あちゃあ」という顔をして、頭をかいた。
「バレたか。参ったな。俺はてっきり、美咲もこの味が好きだと思い込もうとしてたんだが」
「好きなんて言ってないよ。……でもまあ、嫌いじゃないけど」
美咲は自分もスプーンを手に取り、焦げた卵を口に運んだ。
香ばしくて、少し硬くて、懐かしい味がした。
「次は、もうちょっと焦がしてもいいかもね」
「おっ、分かってきたじゃないか。コツはな、ビビらず強火だ」
父が得意げに講釈を垂れ始める。
リビングの照明の下、二つの「失敗作のような」オムライスが並ぶ。
それは決して洗練された料理ではなかったけれど、世界中のどの三ツ星レストランよりも、この家族にお似合いの味がした。
(おわり)